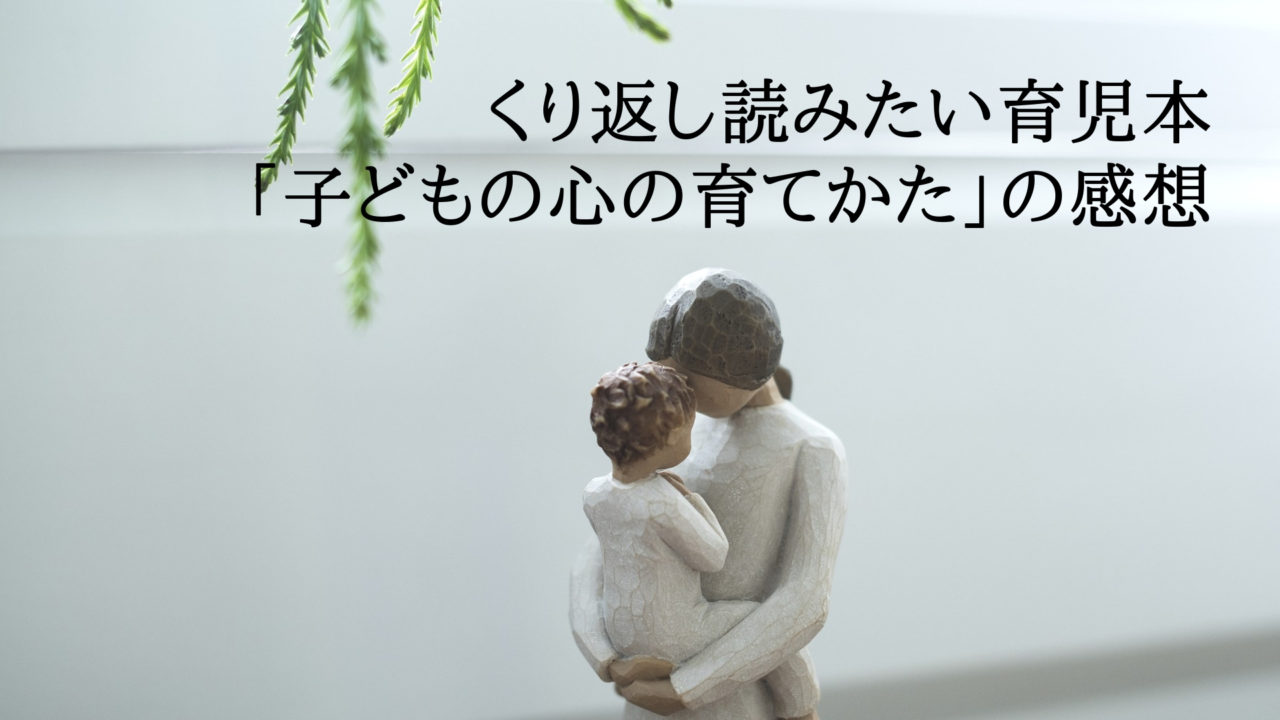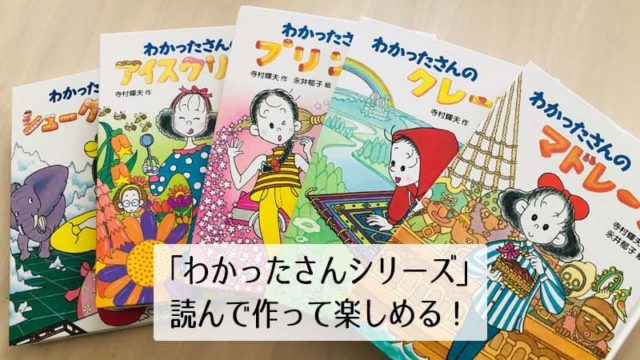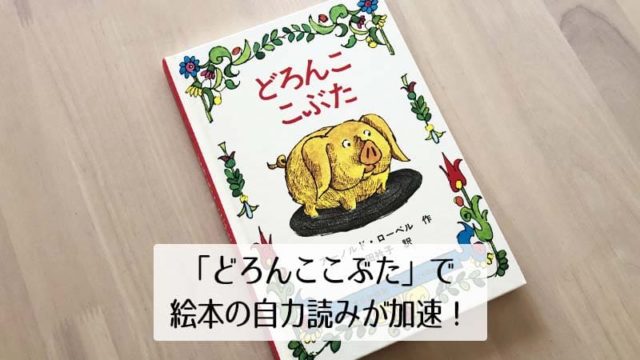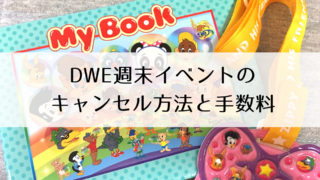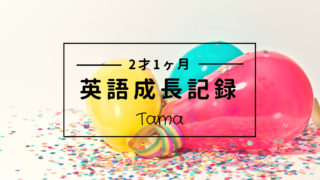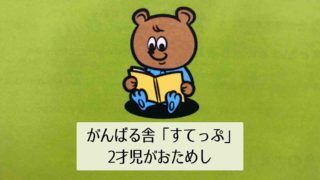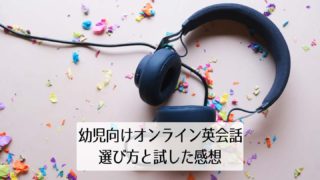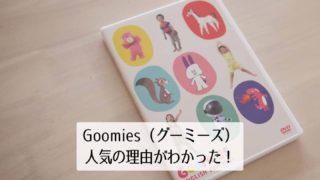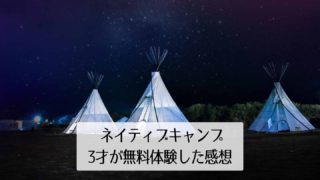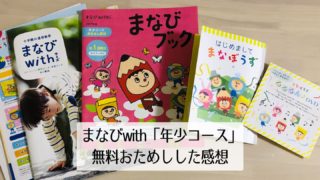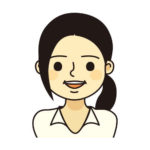こんにちは!いおりです。
子どもがおなかにいるときには「健康に生まれてくれればそれでいい」と思っていました。でもいざ健康に生まれてくると「こんな子になって欲しい」「こんなことができるようになって欲しい」と、どんどん欲張りになってきていることは否定できません。
そんななか、初心に立ち返ることができ、今後も迷ったときに繰り返し読んでいきたいと思ったこちらの本を紹介します!
きっと読んだら、子どもを抱きしめたくなると思います。

すべての項目余すことなく重要事項だったのですが、2才と0才の子を持ち英語育児をしている私が現時点で気をつけようと思った項目だけ、ご紹介します。
トイレトレーニングは褒めすぎず叱りすぎず

我が家はちょうど2才の子どものトイレトレーニングをしているところ。
なんとなく、トイレトレーニングで叱るのはだめということは知っていましたが、なぜだめなのかははっきりとは分かりませんでした。
叱らず、ほめて、焦らず進めればいいんでしょ。という感じ。
本によると、1~3才は自分の衝動や感情を律する自律心を学ぶ時期。
(前略)この時期に子どもは自分の行為に対して叱られるなど否定的な「悪い思い」を過度に経験すると、自分の存在そのものを「恥」とする感覚、自分の存在価値に対する疑惑の感情が生まれてくるといわれています。
なんということでしょう。
厳しくしつけることで身につけることもできますが、でもそれは親の褒め言葉が欲しくてできるようになったこと。
気持ちよく快適なことだからトイレで排泄するのだな、という本来の目的を知る前にトイレトレーニングが完了してしまった場合にのちのち問題が出てくるというのです。
気をつけようと思ったのは、褒めすぎもよくないということ。
なぜなら、失敗したときに親が失望することを教えているようなものだからだそうです。
トイレが成功すると、「わ~!できたね~!」と拍手して一緒に喜んでいた我が家。
正直トレーニングを開始したときは褒めすぎだった気がします。
誕生日かな?ってくらい褒めていたので・・・。
今は割と普通に褒めることができているはず・・・^^;
スポンサーリンク
過保護は心配しなくていい、問題は過干渉

私、過保護は悪いことだと思っていました。
これは「過保護」と思っていたことは実は「過干渉」で、その違いがあいまいになっていたのも原因。
過保護を心配することはありません。過保護というのは、子ども自身がのぞむことを過剰に与えることです。それよりも避けなければいけないのは過干渉です。なぜいけないのかといえば、それは子どもがのぞむことではないからです。
とあるように、子どもが自然に成長・発達していく間に必要なものは子どもが自分で求めるため、求められたものは思う存分与えてあげていいのだそうです。
そして、親ののぞむものを子どもがのぞんでいないのに与えることが過干渉。
これは子どもが欲求不満の状態になってしまい自立へのスタートを妨げることになってしまうのだそう。
そういわれても、子どもの求めることすべてに答えるのは勇気がいりませんか?
たとえばご飯を食べている最中で「ヨーグルトたべる。」と子どもが言ったとき。
この要求に素直に応じるのが嫌な理由は、ヨーグルトを食べてご飯を食べない可能性が出てくるから。
でもこの本によると、子どもがのぞめば好きなだけ食べさせてもいいのだそうです。
この本を読んだ日、食事の最中に「ヨーグルトたべる。」と言ってきた長女に素直にヨーグルトを渡してみました。
長女はとても嬉しそうに食べ、その食事は一度も癇癪を起こすことなく終えられました。
そこで一番感じたのは、私の気持ちが楽だったということ。
子どもに何かを制限させ、子どもがぐずると親にとってもストレスになります。
特に食事の時間って本当にイライラします。
食べ物をこぼしたり、遊んだり、食べてくれなかったり。
でも好きなものだったらすんなり嬉しそうに食べます。
体には良くないかもしれないけど、親と子が楽しく食事の時間を過ごすことができました。
ただ、今回のような要求ならまだいいかなと思うのですが「ご飯いらない」「アイス食べる」と言ったときは・・・?など、本当にすべての要求に100%答えてあげていいのか、エスカレートしないか、不安が残ります・・・
そして、
過保護を恐れる親というのは、干渉したがる親です。ほとんどの場合、こういって間違いないと思います。
この一文にぎくり・・・・。
考えたいのは早期教育のこと。
早期教育に悪いイメージを持っている方って早期教育がこの過干渉の部分に当てはまると思っているからではないでしょうか?
子どもが嫌がっているのに「勉強しなさい!」と過度に勉強させる教育ママは確かに過干渉かもしれませんが、子どもが楽しんでできるように環境を作ったり促したりすることは過干渉には当てはまらないと思います。
早期教育に取り組まれている方のブログを拝見すると、いわゆる「お勉強」の部分だけにフォーカスしている方って実は見たことがないです。
皆さん子どもの健全な成長を一番に考え、さらに子どもの将来を広げるために親が勉強し、悩みながら取り組んでおられます。
この過干渉の部分も、早期教育に力を入れるからこそ気にかけ、子どもが自分からやりたくなるように工夫している方が多いと思います。
だからといって自分も大丈夫、とは限らないので、早期教育の面に限らず過干渉にならないように気にかけながら日々過ごしていきたいところです。
差別感の芽生えに対する教育

これはかなり難しい問題です。
なぜかって、残念ながら私自身の中にも差別の心があるから・・・
性差別とか人種差別とかLGBT差別とか本当に大嫌いです。
でもそれ以外の部分で、自分が差別の気持ちをまったく持っていない!とは言い切れない・・・
そんな私が、子どもに差別感の芽生えを乗り越えさせ、人の能力差に応じて人の価値が決まるなんて事はない、と伝えることができるのか不安ではあるのですが。
なんとしても、これは絶対に教えたい。
近いとことで言うと姉弟。
私自身は3人兄弟の長女ですが、幼いときから妹と弟より父親から愛されていると思っていました。
自分が一番愛されたかったので、一番いい子でいるよう心がけ、父親のご機嫌をとることも小さいときからやっていました。
そのため、下の2人よりも大切に扱われていました。(少なくとも私はそう感じていました。)
母親は兄弟みな平等に愛して接していたと思います。でも父親は違った。
今考えると、子どもが親に愛される努力をしないといけない状況っておかしいです。
そういった自分の経験もあって、強く思うのです。
長女と長男がふたりとも、お互いの能力差に関係なく価値があり、親に愛されていると常に感じていてもらいたい。
むしろ、そんなことを意識する必要もないくらいに、安心した状態でいてほしい。
まとめ
ほんと、全部の項目余すとこなく説明したいところですがネタばれにもなるのでほんの一部だけご紹介させていただきました。
間違いなく私の今後の育児のバイブルになっていきそうです。
また何度も読み返したいです。買ってよかった。
最後に、一番心に響いた言葉を引用させていただきます。
お母さん、お父さん。
どうぞ子どもを甘やかすことを決して恐れず厭わず、一生懸命にかわいがって育ててあげてください。いい子にしているときにかわいがるのではなく、どんなときにも愛してあげてください。
子どもは愛されることで、いい子になるのです。
最後までお読みいただきありがとうございました。